EPISODE 5
山のものを工夫して食べる、狩猟と採取の文化を実食!
ただ山を焼き、種をまくだけ
焼畑は単純だけどすごい農法
椎葉勝さんのもとには、栄養学の専門家である中村学園大学名誉教授の太田英明先生も同行することとなった。勝さんが暮らすのは村の中心部からさらに車で1時間ほどかかる向山日添(むかいやまひぞえ)地区。到着した私たちを、勝さんがまず焼畑へ案内してくれた。


8月に火を入れて約3か月。真っ黒に焼けていた大地には草木が背丈を伸ばし、秋の風にそよいでいる。

太田先生は焼畑を見るのは今回が初めて。
太田「こんなに急勾配だとは思っていませんでした。畑というよりも山そのものですね。」

勝「先人たちはこの土地で生きるため、山を焼いて作物を育ててきました。農薬を使わず、水もやらず、ただ種をまくだけ。私たちが使わせてもらった後も、命が循環して山が再生し、自然がよみがえる。そうすることで昆虫や鳥が生きる場所ができる。単純だけどすごい農法だと思いますよ。」
山を焼く火が土壌の害虫や病原菌を死滅させるから農薬は必要ない。燃えた草木の灰が腐葉土を覆い、土壌中の栄養素を高めるため肥料もいらない。勝さんの手によってまかれた種は、太陽の光と雨水を浴びて育つ。そば、稗(ひえ)または粟(あわ)、小豆(あずき)、大豆(だいず) と4年間輪作した後は、20年以上かけて雑木林に戻す。そして地力が回復した頃に草木を伐採し、再び火を放つ。



今あるものを生かして生きる
先人たちが守り継いだ知恵と技術
1950年頃、焼畑は全国各地で行われていた農法だった。しかし、高度経済成長をきっかけに日本の農業の近代化が進み、焼畑を営む農家の数は大きく減少した。さらに、1992年の「国連環境開発会議」を前に南米や東南アジアの熱帯雨林の破壊の原因が焼畑にあると世界的に報道されたことをきっかけに、“焼畑”への批判が起こったことも衰退の一因とされている。

しかし、勝さんの話を聞くと、椎葉村の焼畑は環境破壊行為ではないと分かる。森林に火を放って乱開発を行う“焼畑”と、椎葉村での“焼畑”は、名称は同じでも中身は別物だ。伝統的な“焼畑”でなら、むしろ焼くことで山がよみがえるのだ。
勝「今では、小規模な焼畑は自然の理にかなった究極の有機農法だと再評価されている。やっと世の中が理解してくれました。」
椎葉村の焼畑は、2015年12月に国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産に「高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム」の一つとして登録されている。

勝さんは妻のミチヨさんと子どもたちと島根県で暮らしていたことがある。
勝「仕事で全国各地を回るうちに、地元の良さが分かるようになった。椎葉村には先人たちが守り継いだ知恵と技術が生きた状態で残っている。あんな場所は他にない、帰りたいなあって思ったんです。」
そして、父の秀行さんの病気を機に、1997年に家族で帰郷。母のクニ子さんと焼畑をするうち、勝さんは先人たちが守り継いだ知恵と技術のすごさを肌で感じたという。
焼畑には山野草と雑穀が育つ。雑穀の種は先祖代々受け継いできた在来種。在来種とは、もともとその土地に存在し、土地の気候風土に適応した遺伝子を持つ。もしも途絶えさせてしまったら、二度と取り戻すことはできない。椎葉家が代々焼畑を守ってきたのには、種を守り、子孫に繋げなければとの使命感に似た思いもあったのだ。


勝「焼畑が5000年前から続けられてきたのには意味と理由があったんだと、その時にようやく理解できて圧倒されました。お金がなくても、山さえあれば生きていける。ここは、今あるものを生かすことで自分も生きられる、そういう場所です。」
山で採れるものを工夫して食べる
山野草も並ぶ野趣あふれる食卓
勝さんが営む民宿『焼畑』に案内してもらう。勝さんの母・クニ子さんは山や植物に関して専門家顔負けの知識を持ち、“クニ子博士”“クニ子おばば”と村人から親しまれた人物。民宿『焼畑』は、クニ子さんを訪ねてくる人々を受け入れるため、1989年にクニ子さんと夫の秀行さんが始めた。私たちは今夜、ここに宿泊する。

宿の台所から根菜を甘辛く炊いているような匂いがする。勝さんの妻・ミチヨさんが夕食の支度をしてくれているのだ。
太田「これらは全部山で採れたものなのですか? いやあ、すごいなあ。こんなに立派ななめこはなかなかお目にかかれませんよ。」



「よかったら、それ」とミチヨさんが指すヤカンには、クロモジのお茶が用意されている。クロモジとは和菓子の楊枝の原料として知られる木。一般的には飲用として知られていないが、1時間ほど煮出すと甘い香りが立ち、すっきりとした後味のお茶になるそうだ。


料理は次々と完成する。干しタケノコのきんぴら、煮しめ、わくど汁、梅みそこんにゃく…。ほとんどの食材が自家栽培か山で採れたものだ。
ミチヨ「山野草は天ぷらにすると苦みがやわらいでおいしく食べられます。今日はスイカズラ、ゲンノショウコ、ヒメジオン(ヒメジョオン)、ヨモギ、ヤマゼリの葉、コアカソ、大根葉、ミツバ。すべてうちの山で採れたものです。春になったらもっと種類が増えますよ。」

太田「山野草の中でも、毒素の有無などを知恵で識別して食事に取り入れているのですね。今夜は焼畑で栽培した穀物も使いますか?」
ミチヨ「わくど汁には焼畑で作ったそば粉を使っています。香りが強く、粘りがあるのが特徴です。食べて確かめてみてください。」

椎葉村には人間の食の原点がある
焼畑や採取で得られる作物は栄養満点
いつの間にか外はすっかり日が暮れて、肌寒くなっていた。

勝「田舎の料理だけど、食べてみてください。わしはこれが“原点の味”だと思っています。現代の人が口にするのは人工的に育てられた肉や魚が多い。わしの母親は魚も肉もほとんど食べなかったけど、山を歩き回り山のものを食べて、ストレスなく生きていました。同じ土地のものを食べるというのが、人間の食の原点じゃないでしょうか。」

勝「母親は99歳で死ぬまで頭もしっかりしていましたよ。雑穀が好きだった父親は90歳近くまで生きました。食べて生きているわけですから、何を食べるかで生き方も体も変わると思いますよ。」
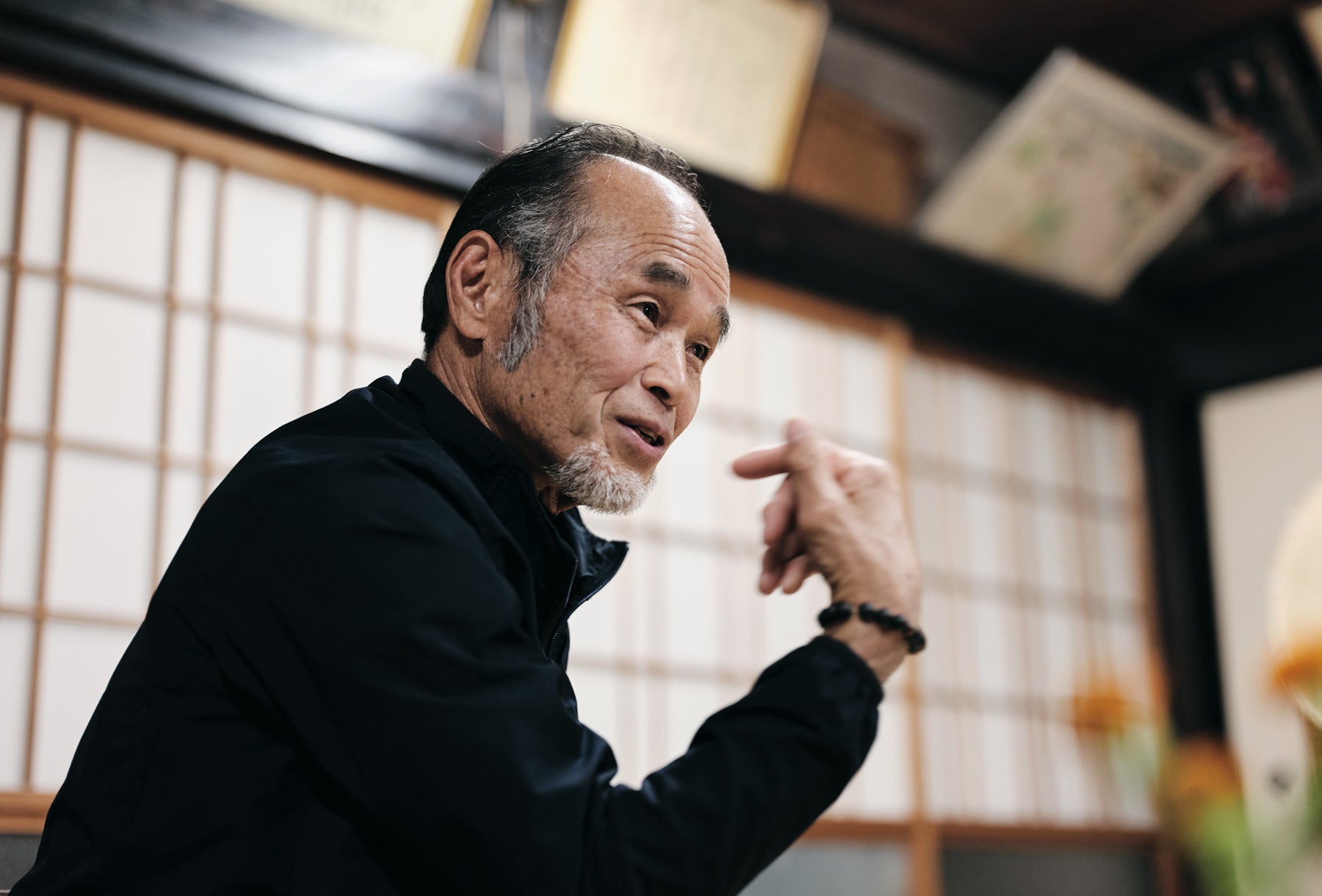
太田「そうですね、現代の日本人は脂質含有量が多い欧米化した食事が中心となっています。脂質の多い食事を続けると、がん、糖尿病、心筋梗塞といった生活習慣病の発症が早められる とされていて、このことが日本人の健康維持における大きな課題となっています。」


太田「その点、焼畑や自然からの採取によって得られる植物系の食材はバリエーションが豊富です。野菜や果実だけでなく、菌類と藻類の共生体である地衣類のイワタケといった珍味もありましたね。さまざまな栄養素をバランス良く摂取でき、厳しい労働を支えるエネルギー源となっています。 そこに運動と食事、休養が十分に取れる生活リズムが加わるのだから、健康で長生きできるのでしょうね。」



勝さん自身も幼い頃は主に稗や粟、小豆、大豆を食べて育った。米は盆と正月に食べる程度。魚にいたっては、魚の匂いすら知らなかったほど食べる機会がなかった。
勝「その頃、ひえずーしーはごちそうでした。猟師は山小屋に1週間泊まり込んでシシやシカを獲り、その肉を村の人たちにも分けてくれよった。山では貴重なたんぱく質源 だから、塩漬けで保存して、少しずつ食べるんです。もったいないからと毛も焼いて食べとったですよ。」

太田「ひえずーしーは非常に興味深い料理です。稗にイノシシの肉を合わせることで、栄養学的にたんぱく質と脂質、炭水化物のバランスが取れた食事になると考えられます。」
勝「へえ、面白いですね。まあ、一度食べてみてください。せっかくですから、明日のお昼ごはんにひえずーしーを用意しますよ。」
夕食後、勝さんが椎葉神楽を披露してくれた。神楽は神に捧げる歌や舞として村内の26地区で伝承されており、集落ごとに演目やスタイルは異なるが、祭壇にイノシシを供えたり、舞の一部として雑穀をまくなど、ここにも狩猟と採集の文化が見て取れる。

築100年を超えるという古民家に響く歌声と太鼓の音に酔いながら、頭の中ではひえずーしーへの想像と期待が広がり続けていた。


