「九州農家めし」
作り手だからこそ知るとっておきの話


新垣さんの「ゴーヤーチャンプルー」
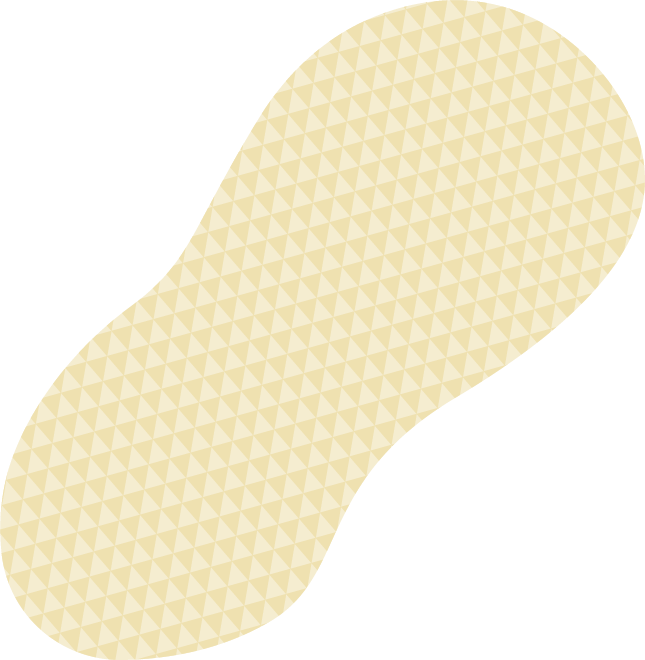


しんがき・ひろし/1969年、沖縄県糸満市出身。ゴーヤーやモロヘイヤ、ピーマン、キュウリなどを栽培する農家に生まれる。造園業、鉄鋼業などを経て、2000年に実家を継ぐ形で就農。現在はゴーヤーを中心に、キャベツや花卉(かき)のストレリチアを生産している。
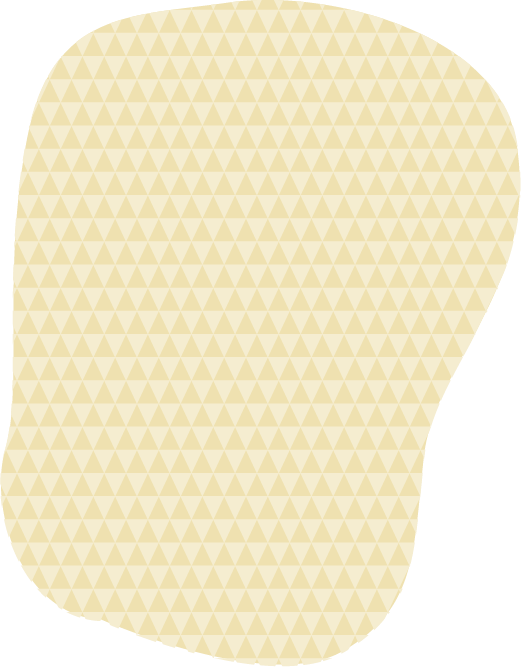

生命力あふれるゴーヤーの苗
艶めく実はずっしりと重い!
艶めく実はずっしりと重い!
ビニールハウスに足を踏み入れた途端、肌にまとわりつくむわっとした湿った空気。同時に、ゴーヤー特有の青々しい香りが鼻の奥までぐっと入り込んできます。葉とツルは網のようにびっしりと繁っており、苗の根元は直径約4cmでゴツゴツとして木の幹のよう。真夏の日差しを浴びるゴーヤーは、見るからにずっしりと重みがあります。
元気いっぱいのゴーヤーを管理しているのは、新垣洋さん。約2000坪の畑で年間約35tを出荷する家で、春夏は成長が早い群星(むるぶし)、秋冬は気温が下がっても収量が落ちにくい汐風(しおかぜ)と、品種を変えながら年間を通して栽培しています。
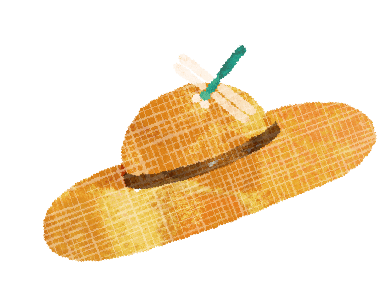
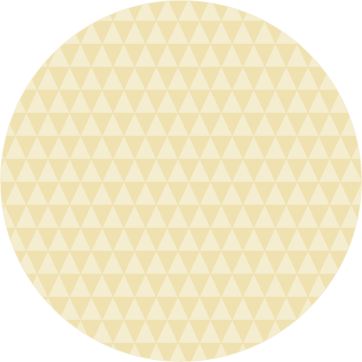

実家を継ぐ形で就農
今ではゴーヤー中心の生活に
今ではゴーヤー中心の生活に
新垣さんは造園業、鉄鋼業などを経て、2000年に実家を継ぐ形で就農しました。幼い頃から農作業を手伝っていたものの、「特にゴーヤーに思い入れがあって就農したわけではなかった」と話す新垣さん。今ではほかの作物の作業をしていても、空き時間ができるとついゴーヤーのハウスに足が向くそうです。
新垣さんのゴーヤー栽培では、成長後に葉やツルが混み合うのを防ぐために、一般的には3m間隔とされる苗の植え付けを、4.5~5m間隔まで広げているのだとか。また、定植から40~50日間は交配させずに苗自身に体力を付けさせるなど、独自の工夫を重ね、丁寧にゴーヤーを育てています。


真夏のハウスに満ちる
静かな情熱
「手をかけた分だけ応えてくれる」
静かな情熱
「手をかけた分だけ応えてくれる」
新垣さんは「ゴーヤーは手をかけた分だけ応えてくれる」との信念から、丁寧な管理作業を欠かしません。沖縄は日射量が多いためハウス内の温度が上がりやすく、夏の日中は40~50度に達することも。夏の熱気に押されそうになりながらもハウスをこまめに見回り、黙々と葉かきや下枝掃除を行う姿からは静かな情熱を感じます。
新垣さんが好きなのは、苦味の穏やかなゴーヤー。ゴーヤーは成長するごとに苦味が穏やかになり、果肉はジューシーに育つため、長さが30cm以上になるまでじっと待つそうです。そして、実の表面の粒(ちりめん状態のイボ)がぷりっと膨らんで光沢が出てきたら収穫のサイン。この見極めもプロの技です。

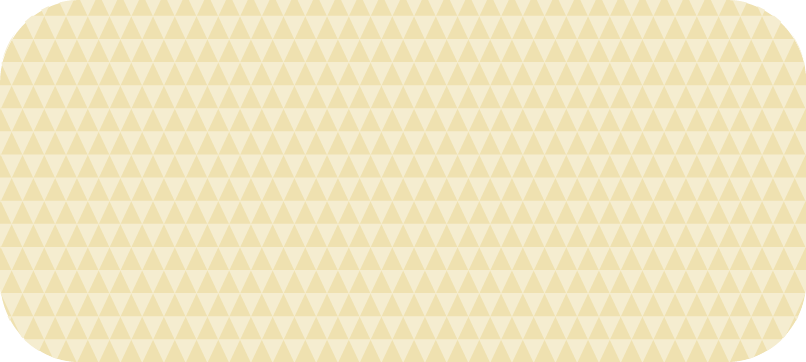

実りを信じてゴーヤーと向き合う
おいしさを届ける取り組みにも意欲
おいしさを届ける取り組みにも意欲
新垣さんは幼い子どもたちにもゴーヤーを食べる機会を持ってほしいと、地元の小学校の学校給食にゴーヤーを提供するなど、おいしさを届ける取り組みにも意欲的です。現在、沖縄全体のゴーヤーの生産者数は高齢化や他作物への転換により減少傾向ですが、新垣さんはゴーヤーにまっしぐら。猛暑の中での作業や、台風による被害など、大変だと感じることはあっても、試行錯誤と苦労の先に喜びがあると信じているからです。
好きなゴーヤー料理を新垣さんに尋ねると「やっぱりチャンプルーでしょう!」と即答。さあ、そのレシピをご紹介しましょう。
九州農家めしレシピ


新垣さんの
「ゴーヤーチャンプルー」
ゴーヤー料理の定番「ゴーヤーチャンプルー」を、ゴーヤーを知り尽くした生産者が作るとどうなるでしょうか? 新垣さんのこだわりは、ゴーヤーを炒める前にかつおだしでさっと軽く火を通しておくこと。苦味成分のモモルデシンが水に溶けて抜けるだけでなく、ゴーヤーがかつおだしの旨みをまとってよりおいしく仕上がります。島豆腐が手に入らない場合は、しっかりと水切りをした木綿豆腐で代用してください。
材料
- ・ゴーヤー:1本(250g)
- ・島豆腐:1/2丁(450g)
- ・ポークランチョンミート:1/2缶(150g)
- ・卵:1個
- ・サラダ油:大さじ1
- ・だしの素(粉末):1袋(8g)
- ・かつおだし(だし汁):適量
つくりかた
- 1

ゴーヤーはワタと種を取り除き、好みの厚さの半月切りにする。
- 2

島豆腐を適当な大きさに切り、電子レンジで2分加熱して水切りする。
- 3

ポークランチョンミートは食べやすい大きさに切る。
- 4

フライパンに①のゴーヤーを入れて火にかけ、少量のかつおだしを加えて半生状態までさっと火を通す。
- 5

③のゴーヤーをザルにあげる。
- 6

フライパンにサラダ油を熱し、ゴーヤーとポークランチョンミート、島豆腐を炒め合わせる。
- 7

だしの素(粉末)で味を調える。
- 8

溶き卵を回し入れ、ふたをして火を止める。
- 9

余熱で卵に火が通ったら器に盛る。

